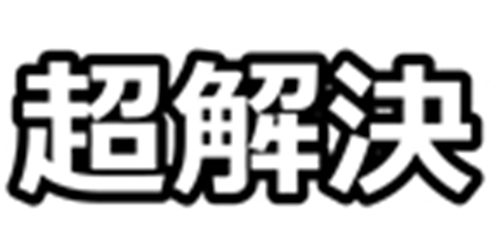目次
1944年、山あいのリゾート地で決まった未来
1944年夏、第二次世界大戦の終結が見えてきたころ。
アメリカ東部、ニューハンプシャー州の小さな町ブレトン・ウッズに、44か国の代表が集まりました。
会場となったのは森に囲まれた高級ホテル。世界経済の新しいルールを話し合うための歴史的な会議が開かれたのです。
ここで決まった仕組みが「ブレトン・ウッズ体制」。戦後の国際金融システムの礎となり、ドルを基軸通貨とした新しい世界が始まりました。
なぜ新しい通貨制度が必要だったのか
戦争で疲弊した世界
ヨーロッパ諸国は戦争で経済がボロボロになり、金の保有量も大きく減っていました。
一方でアメリカは戦火を免れ、経済的にも軍事的にも突出した力を持っていました。
「戦後秩序を安定させるには、アメリカが主導する通貨体制が不可欠」――そんな空気が広がっていたのです。
大恐慌の苦い記憶
1930年代、世界恐慌のさなかに各国は保護主義へと走り、貿易を締め出し合いました。
為替の乱高下、ブロック経済の分断。これが再び起きてはならない――。その強い反省が、安定した国際通貨制度をつくる動機になりました。
ブレトン・ウッズ体制の仕組み
ドル=金、そして各国通貨
この体制の核心はシンプルでした。
米ドルを世界の基軸通貨とし、1オンス=35ドルで金と交換可能にする。
各国通貨はドルに固定され、ドルを通じて間接的に金と結びつく――。
ドルはまさに「世界経済の錨(いかり)」となったのです。
固定相場制とIMF
各国はドルに対して一定の為替レートを維持する義務を負いました。大幅な調整が必要な場合は、IMF(国際通貨基金)の承認が必須。
また、戦後復興や途上国支援を担う世界銀行も設立され、国際協調の枠組みが整いました。
どんなメリットがあったのか
- 為替が安定し、企業が安心して国際取引を拡大できた
- ドルが金と結びついたことで通貨乱発が抑えられ、インフレが制御された
- 投機的な資本移動が制限され、金融市場が安定した
日本や西ドイツはこの環境の中で高度経済成長を実現しました。まさに「安定こそ最大の成長戦略」だったのです。
ドルの信頼が揺らいだ瞬間
アメリカの財政赤字
1960年代、アメリカはベトナム戦争と大規模な社会政策で財政赤字を膨らませました。
世界は次第に「ドルは本当に金と交換できるのか?」と疑い始めます。
各国がこぞってドルを金に替えようとしたことで、ドル=金の関係は急速に揺らいでいきました。
ニクソン・ショック
1971年8月、ニクソン大統領はテレビ演説で「ドルと金の交換停止」を発表。
それは世界に衝撃を与え、「ブレトン・ウッズ体制」の終焉を告げる出来事となりました。
変動相場制へ
1973年、主要国は変動相場制へ移行。以後、通貨の価値は市場の需給で決まる現在の仕組みへと変わっていきます。
体制が残したもの、そして現代への教訓
- 戦後復興と高度経済成長を支えた安定した為替環境
- 体制崩壊を契機とした金融市場の自由化
- ドルの基軸通貨としての地位確立
そして今もなお、基軸通貨を巡る議論は続きます。人民元やデジタル通貨の台頭が話題になりますが、
歴史が教えるのは「基軸通貨には絶対的な信頼が必要だ」という一点。ドルが“世界の錨”になれたのも、その信頼ゆえだったのです。
まとめ
ブレトン・ウッズ体制は、戦後世界を安定させた歴史的な金融システムでした。
やがてアメリカの経済的負担が限界に達し、1971年のニクソン・ショックで幕を閉じましたが、
この体制の経験は、現在の国際通貨制度を考えるうえで欠かせない教訓を残しています。
歴史は繰り返す――基軸通貨の信頼をめぐる物語は、今も続いているのです。